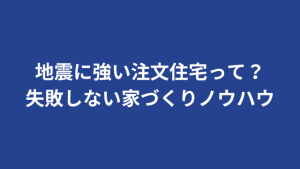制震ダンパー「MAMORY」について
■ 制震ダンパー「MAMORY」について 住友ゴム工業株式会社の開発した制震ダンパー「MAMORY」は、鋼板と高減衰ゴムを用いて作られた制震装置です。 特殊高減衰ゴムが地震の揺れにより変形することで、地震エネルギーを熱エネルギーに変換吸収し、建物の揺れ及び損傷を抑えます。 デックスでは制震ダンパー「MAMORY」を全棟標準採用することにより、コストを大幅に抑えることが可能となり、お客様にご安心いただける制震性を実現させていただいております。 制震とは、地震の振動を制振(制震)機構により抑制する技術となり、制震機構によって建物の揺れを減少させ、構造体への損傷が軽減されます。大規模な地震や繰り返し起こる地震(余震)にも有効です。 ■ 特殊高減衰ゴムの運動エネルギー吸収力 「MAMORY」の制震性能は特殊な高減衰ゴムの特性を利用しています。同じ高さから、一般的なゴムと高減衰ゴムのボールを落とすと、一般的なゴムのボールはよく跳ねるのに、高減衰ゴムのボールは全く跳ねません。 これにより高減衰ゴムが、運動エネルギーを熱エネルギーに変換し、吸収している事がわかります。住宅に設置された「MAMORY」は建物に層間変形が生じると、仕口部の角度が変化し、制震装置の伸び・縮みにより、高減衰ゴムが変形します。高減衰ゴムの変形によって、地震エネルギーを熱エネルギーに変換し、建物の揺れ幅を抑えてるのです。 ■ 震度6強~7相当の巨大地震に5回耐える 京都大学防災研究所において、実大実験を行った結果、熊本地震前震級の地震波と本振級の地震波を2回加えても、MAMORYを装着した試験体は倒壊しませんでした。これによりMAMORYにより建物の耐震性が向上する事が実証されました。 効果の実証により、「MAMORY」は熊本城天守閣の修復工事や京都・東本願寺などの歴史的建造物にも採用されています。 ■ 設置のしやすさと高い設計自由度 制震ダンパー「MAMORY」は柱と梁・土台が交差する箇所に設置します。構造用面材との併設が可能な為、設計の自由度を損なう事なく設置が可能です。 「MAMORY」の制震効果は60年(※促進劣化試験結果による)、またメンテナンスーの必要もない為、安心の生活を長期間支えてくれます。 ■ デックスのハイブリット制震工法 デックスが提案する構造は、高耐震構造パネルによるモノコック構造による地震力に耐える耐震構造と、高減衰ゴム制震ダンパーの地震力を逃がす制震工法を組み合わせた、ハイブリッド制震工法です。 巨大地震が起こった際に、地震に耐えるには建物の耐震構造が必要ですが、先の熊本の地震のような繰り返し起こる余震や度重なる地震に対して、建物を守るには、建物に加えられる地震力を外に逃がし、基礎や木部の接合金物に対する負担を軽減する必要があります。 デックスでは、耐震と制震を組み合わせることで、「柔軟な立方体」を形成し、大きな地震力が繰り返し起こっても、建物にかかる負担を最小限に抑え、より長寿命な構造躯体をつくります。 [blogcard url="/news/3824"] デックスの地震に強いパワービルド工法